ペットボトル症候群とは?症状をわかりやすく解説しながら予防と対策についても詳しくご紹介します
- Color Voice
- 2025年7月17日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月6日

ペットボトル症候群とは何か?
ペットボトル症候群とは、正式には「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれる状態です。糖分を多く含む清涼飲料水を過剰に摂取することで、血糖値が異常に上昇し、急性の糖尿病のような状態に陥ることがあります。
特に若年層や働き盛りの世代に増えており、ペットボトル飲料を頻繁に飲む習慣がある人に多く見られます。
主な原因は糖分の過剰摂取
ペットボトル症候群の主な原因は、糖分を大量に含む飲料の頻繁な摂取です。スポーツドリンクや炭酸飲料、フルーツジュースなど、清涼感があり飲みやすい飲料には驚くほど多くの糖分が含まれています。
特に喉が渇いたときに一気に飲むと、短時間で大量の糖分を摂取することになり、血糖値が急上昇します。これが繰り返されることで、体内のインスリンの働きが追いつかなくなり、ペットボトル症候群が引き起こされます。
ペットボトル症候群の症状とは
ペットボトル症候群になると、次のような症状が現れることがあります。
・のどの渇きが異常に強くなる
・頻尿や尿量の増加
・倦怠感や疲れやすさ
・急激な体重減少
・吐き気や腹痛
・意識がぼんやりする
症状が進行すると、意識障害や昏睡に至るケースもあり、非常に危険です。自覚症状が少ないまま進行することもあるため注意が必要です。
誰でもなりうる現代病の一つ
ペットボトル症候群は、特別な体質の人だけがかかるものではありません。普段からペットボトル飲料を多く飲む人なら、誰でも発症の可能性があります。
特に、運動習慣がなく、野菜やタンパク質の摂取が少ない食生活を送っている場合は、発症リスクがさらに高まります。夏場や喉が渇きやすい時期には特に注意が必要です。
ペットボトル症候群の予防法
予防のためには、生活習慣の見直しがとても重要です。
水やお茶を中心に水分補給をする
清涼飲料水ではなく、糖分を含まない飲み物を選びましょう。
糖分表示を確認する習慣をつける
飲料のラベルをチェックし、糖質量を把握することが大切です。
1日あたりの清涼飲料水の量を決める
どうしても飲みたい場合は、量を制限して飲むようにしましょう。
バランスの良い食事を心がける
血糖値のコントロールには、食物繊維やタンパク質が有効です。
怪しいと思ったら早めに受診を
喉の渇きや疲労感が続くときは、自己判断で放置せず、早めに内科や糖尿病専門医を受診しましょう。血液検査で血糖値をチェックすることで、早期発見・早期治療につながります。
特に夏場は体調を崩しやすく、他の症状と重なることもありますので、気になる不調がある場合はすぐに医師に相談することが大切です。
健康的な水分補給で暑さを乗り切る
ペットボトル症候群は、正しい知識と意識で十分に防ぐことができる現代病です。清涼飲料水の飲みすぎには注意し、体にやさしい水分補給を心がけましょう。
暑い季節を元気に乗り切るためにも、今こそ生活習慣を見直すタイミングかもしれません。健康的な毎日を送るために、今日からできることを始めてみてください。



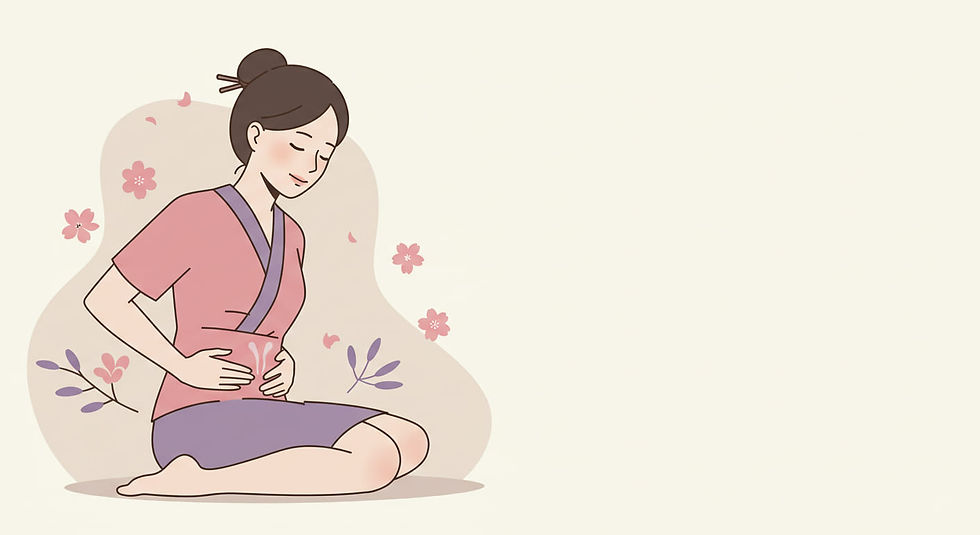

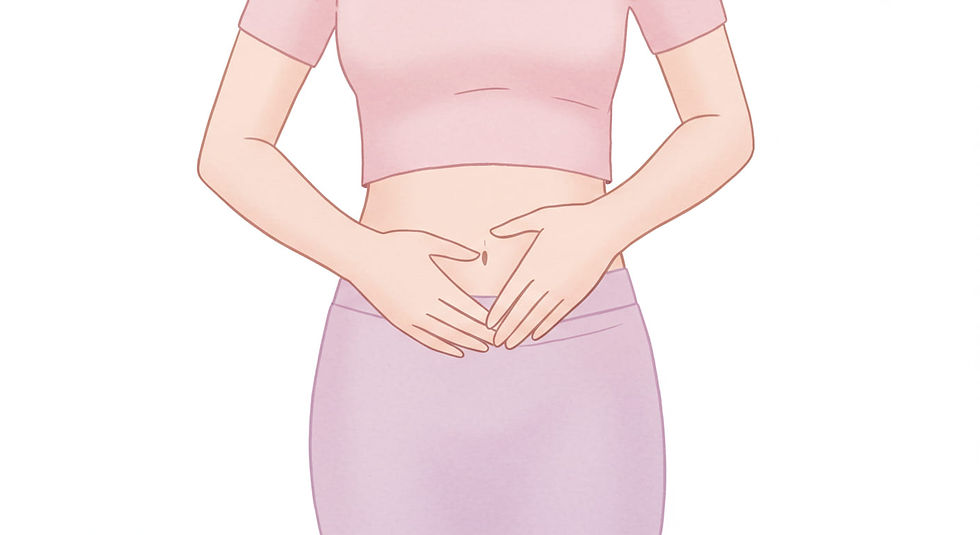
コメント